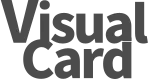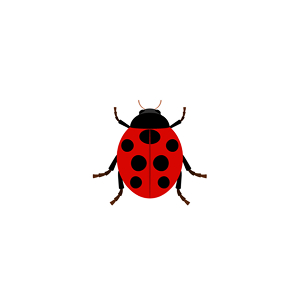言葉と絵、二つのカギで開く「わかる」の扉
子どもの脳は、大人が思う以上に視覚情報を効率的に処理する能力を持っています。教育心理学の分野では、アラン・パイヴィオが提唱した「二重符号化理論」が広く知られています。
これは、情報は言葉などの「言語的情報」と、イメージなどの「非言語的(視覚)情報」という二つの経路で脳に記憶され、両者が結びつくことで記憶がより強固になるという理論です。
つまり、言葉で聞かせ、同時に絵で見せることは、子どもの頭の中に二つの異なるフック(手がかり)を作ることになり、理解と記憶を格段に助けるのです。
幼児教育における視覚情報の活用は、単なる暗記のためではなく、子どもの「わかった!」という喜びを引き出すための強力な手段と言えます。
出典: Paivio, A. (1986). Mental representations: A dual coding approach. Oxford University Press.
1:絵本の読み聞かせ - 物語世界への没入体験
絵本は、視覚学習の最も代表的で効果的なツールです。親が読み聞かせる言葉(聴覚情報)と、ページに広がる絵(視覚情報)が子どもの頭の中で結びつくことで、物語への理解が飛躍的に深まります。
例えば、「おおきな まるい りんご」という言葉を聞きながら、赤く艶やかなリンゴの絵を見ることで、「おおきい」「まるい」「りんご」といった抽象的な概念が具体的なイメージと直結します。
この体験の繰り返しが、語彙力や世界の仕組みを理解する土台を築きます。さらに、登場人物の表情豊かな絵は、言葉だけでは伝わりにくい「嬉しい」「悲しい」といった感情の理解を助けます。
米国の研究では、ただ読むだけでなく、絵を指差しながら「これは何かな?」「ワンワンはどんな気持ちかな?」と対話を取り入れる「対話型読み聞かせ」が、子どもの言語能力を特に高めることが示されています。
出典: Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. Child Development, 69(3), 848–872.
2:図形ブロックやパズル - 手で考える力の育成
図形ブロックやパズル遊びは、子どもが自らの手で視覚情報を操作し、論理的思考力を育む絶好の機会です。
様々な色や形のブロックを積んだり、並べたりする中で、子どもは「大きさ」「高さ」「重さ」「バランス」といった物理的な概念を感覚的に学びます。これは、言語を介さずに空間認識能力を鍛える重要なプロセスです。
見本の絵と同じ形をブロックで組み立てる遊びは、二次元の視覚情報(絵)を三次元の立体物として再構築する高度な認知活動であり、空間把握能力や問題解決能力を養います。
複数の研究により、幼少期のブロック遊びの経験が、その後の算数や幾何学分野の学業成績と正の相関があることが報告されています。
手と目を使った試行錯誤そのものが、机上の学習では得られない「生きた知識」となるのです。
出典: Wolfgang, C. H., Stannard, L. L., & Jones, I. (2001). Block play performance among preschoolers as a predictor of later school achievement in mathematics. Journal of Research in Childhood Education, 15(2), 173–180.
3:お絵かき - 「見た世界」を表現する思考の整理
お絵かきは、単なる遊びではなく、子どもが自分の中にある世界(内的イメージ)を視覚化し、表現する重要な学習活動です。
子どもは、家族の顔、ペット、楽しかった出来事など、心に残ったイメージを紙の上に描き出します。この「描く」という行為は、頭の中にある漠然とした情報を整理し、その特徴を捉え直す思考のプロセスそのものです。
子どもが描いた絵について「これは誰を描いたの?」「ここで何をしているの?」と大人が問いかけることで、子どもは自らの視覚表現を言葉で説明しようとします。
このやり取りは、視覚情報と言語情報を結びつけ、コミュニケーション能力や客観的に物事を捉える力を育みます。
心理学者のヴィゴツキーは、お絵かきのような象徴的活動が、抽象的な思考など、より高度な精神機能の発達の基礎となると指摘しています。
出典: Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.
まとめ
ここまで見てきたように、重要なのは、特別な教材で訓練することではなく、日常生活の中に視覚的な要素を豊かに取り入れることです。
絵本を一緒に楽しみ、ブロックで遊び、自由にお絵かきをさせる。そして、子どもが見ているもの、作ったものについて「これは面白い形だね」「どうしてこうなったのかな?」と対話し、興味を共有すること。
日常のすべてが学びのチャンス。こうした親子のコミュニケーションを通じて、子どもの中では言葉とイメージが固く結びつき、知的好奇心が育まれていきます。
視覚情報は、子どもたちが世界を理解するための強力な羅針盤です。その羅針盤を親子で一緒にのぞき込むように、日々の生活を楽しみながら、子どもの「わかる力」を自然に伸ばしていきましょう。