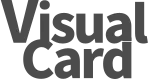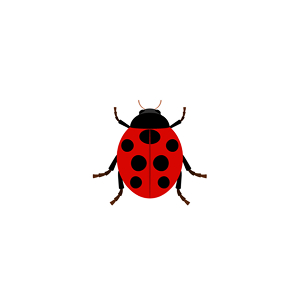「子どもとの時間、どうやって遊んだらいい?」「この遊び方で、子どものためになっているのかな?」そんな風に感じたことはありませんか。
忙しい毎日の中で、子どもとの時間はかけがえのないもの。その時間を、もっと豊かで意味のあるものにできるとしたら、素敵ですよね。
実は、特別な知育玩具や難しい教材を使わなくても、普段の「遊び」に少し工夫を加えるだけで、子どもの言葉の発達を効果的に促す「言語刺激」の機会に変わります。
この記事では、親子のコミュニケーションを楽しみながら、子どもの「話したい」「伝えたい」という気持ちを育む、具体的なアイデアを3つご紹介します。いつもの遊びをワンランクアップさせて、子どもの言葉の世界を一緒に広げていきましょう。
会話が生まれる「お店屋さんごっこ」
ごっこ遊びは、子どもの想像力や社会性を育むだけでなく、言語能力を高める絶好の機会です。特に「お店屋さんごっこ」は、役割分担によって自然な会話のやり取りが生まれます。
おもちゃや積み木、折り紙など、身の回りにあるものを「商品」に見立てて並べてみましょう。親がお店屋さん役になって「いらっしゃいませ!」「今日は美味しいリンゴがありますよ」と元気よく声をかけると、子どもはお客さんとして「これをください」と応じやすくなります。慣れてきたら役割を交代し、子どもに店員さん役を任せてみましょう。
「これはいくらですか?」「おすすめはどれですか?」など、少し複雑な質問を投げかけることで、子どもは一生懸命に言葉を探して表現しようとします。
おままごとのポイントは、子どもの言葉を急かさずに待ち、豊かな表情や身振り手振りを交えて楽しむことです。
五感を刺激する「粘土遊び」
粘土遊びは、指先の感覚を養うだけでなく、五感から得た情報を言葉に結びつけるトレーニングに最適です。
「つめたいね」「やわらかいね」といった触覚に関する言葉、「びよーんと伸ばそう」「ころころ丸めよう」といったオノマトペ(擬音語・擬態語)は、子どもにとって楽しくて覚えやすい言葉です。まずは親子で一緒に粘土に触れ、感じたことをそのまま言葉にして伝えてみましょう。
赤や青の粘土を混ぜながら「あおとあかを混ぜると、むらさきになったね!」と色の変化を実況するのも良いでしょう。子どもが何かを作ったら、「わあ、長いヘビさんだね」「まんまるのお団子ができたんだね」と、具体的に言葉で形を表現してあげることがポイントです。
感覚的な体験と言葉が結びつくことで、子どもの語彙は豊かになり、表現の幅も広がっていきます。
対話が広がる「絵本の読み聞かせ」
絵本の読み聞かせは、言語刺激の基本ですが、少し工夫するだけで「対話」を生む豊かな時間になります。ただ文章を読むだけでなく、絵本の表紙を見ながら「どんなお話だと思う?」と問いかけることから始めてみましょう。
物語の途中でも、「うさぎさん、泣いているね。どうしてかな?」「次は何が出てくると思う?」といったように、子どもの気持ちや予測を引き出す質問を投げかけるのが効果的です。
また、絵の細部に注目し、「あ、ちょうちょが飛んでいるね」「お花が何本咲いているかな?」など、絵から情報を読み取る練習も語彙力アップにつながります。
読み終わった後には、「どこが一番面白かった?」と感想を聞き合う時間も大切にしましょう。物語について対話することで、子どもは内容の理解を深め、自分の言葉で考えや感情を表現する力を養うことができます。
まとめ
今回ご紹介した3つのアイデアは、どれも特別な準備を必要とせず、家庭ですぐに実践できるものばかりです。
大切なのは、完璧な言葉を教え込むことではなく、親自身が子どもとの対話を心から楽しみ、子どもの「伝えたい」という気持ちに寄り添う姿勢です。
子どもが言い間違えたり、うまく言葉にできなかったりしても、急かさずにじっくりと耳を傾けてあげてください。親が楽しそうにしていると、子どもも安心して言葉を発するようになります。
日々の遊びの中にほんの少し「言葉」を意識するだけで、子どもの言語能力は自然と育まれていきます。親子のコミュニケーションを深めながら、お子様の健やかな言葉の発達を、あたたかく見守っていきましょう。